筋トレとは、筋肉を壊す行為だ。
トレーニングのたびに筋繊維を破壊し、再生によって強くする。
つまり、筋トレは文字通り「自傷行為」である。
だが、もうひとつの意味で、筋トレは精神的な自傷でもある。
心に傷を抱えた人が、その痛みを筋肉痛へと置き換える。
「死にたすぎて筋トレに励む」という言葉を聞いたことがある。
それは、痛みを消すためにあえて痛みを作り出す行為だ。
痛みを燃料に動く人たち ― ネガティブドリブ
人は時に、コンプレックスや孤独、絶望を原動力にして努力する。
貧しさ、不器用さ、容姿への劣等感、性的マイノリティとしての生きづらさ――
それらの痛みをエネルギーに変えて走り出す人がいる。
これは昭和的な「ハングリー精神」に似ているが、少し違う。
ハングリー精神は「満たされない現実を超えたい」という健全な野心だが、
痛みを糧にする人は「感じたくない感情を麻痺させたい」という逃避のニュアンスを含む。
「死にたすぎて筋トレに励む」はその最たる例だ。
肉体の痛みが、心の痛みを上書きしてくれるから。
ポジティブドリブン ― 好奇心で動く人
一方で、コンプレックスがなくても努力を続けられる人がいる。
彼らは「好きだから」「成長が楽しいから」というポジティブな動機で動く。
結果ではなく、過程そのものを楽しむタイプだ。
このようなポジティブドリブンな人は、燃え尽きにくい。
痛みではなく好奇心を燃料にしているため、努力が自然体で続く。
ネガティブドリブンの限界
私は、最終的にポジティブドリブンが勝つと思っている。
なぜなら、ネガティブドリブンの努力は「痛みの存在」に依存しているからだ。
努力が実を結び、心の傷が癒えてしまうと――
動機そのものが消える。
つまり、心の回復が進むほど、努力の炎が消えていく。
このパラドックスこそが、「筋トレという自傷行為」の本質だ。
痛みを癒すために始めた努力が、痛みを失った瞬間に続かなくなる。
永続する成長とは
ポジティブドリブンの人は、結果が出てもまた次の課題を見つける。
「もっと上手くなりたい」「もっと知りたい」という探究心が尽きない。
努力が義務ではなく、生き方そのものになっている。
ネガティブドリブンが「過去から逃げる力」だとすれば、
ポジティブドリブンは「未来へ進む力」だ。
結び
筋トレは、体を壊して強くする行為。
そして、時に心を壊して保つ行為でもある。
痛みを抱えながらでも前に進むその姿は、決して否定されるものではない。
けれど、いつか痛みが癒えたとき――
その先で「楽しさ」によって動ける自分に出会えたなら、
それが本当の意味での筋肉の再生なのだと思う。〆

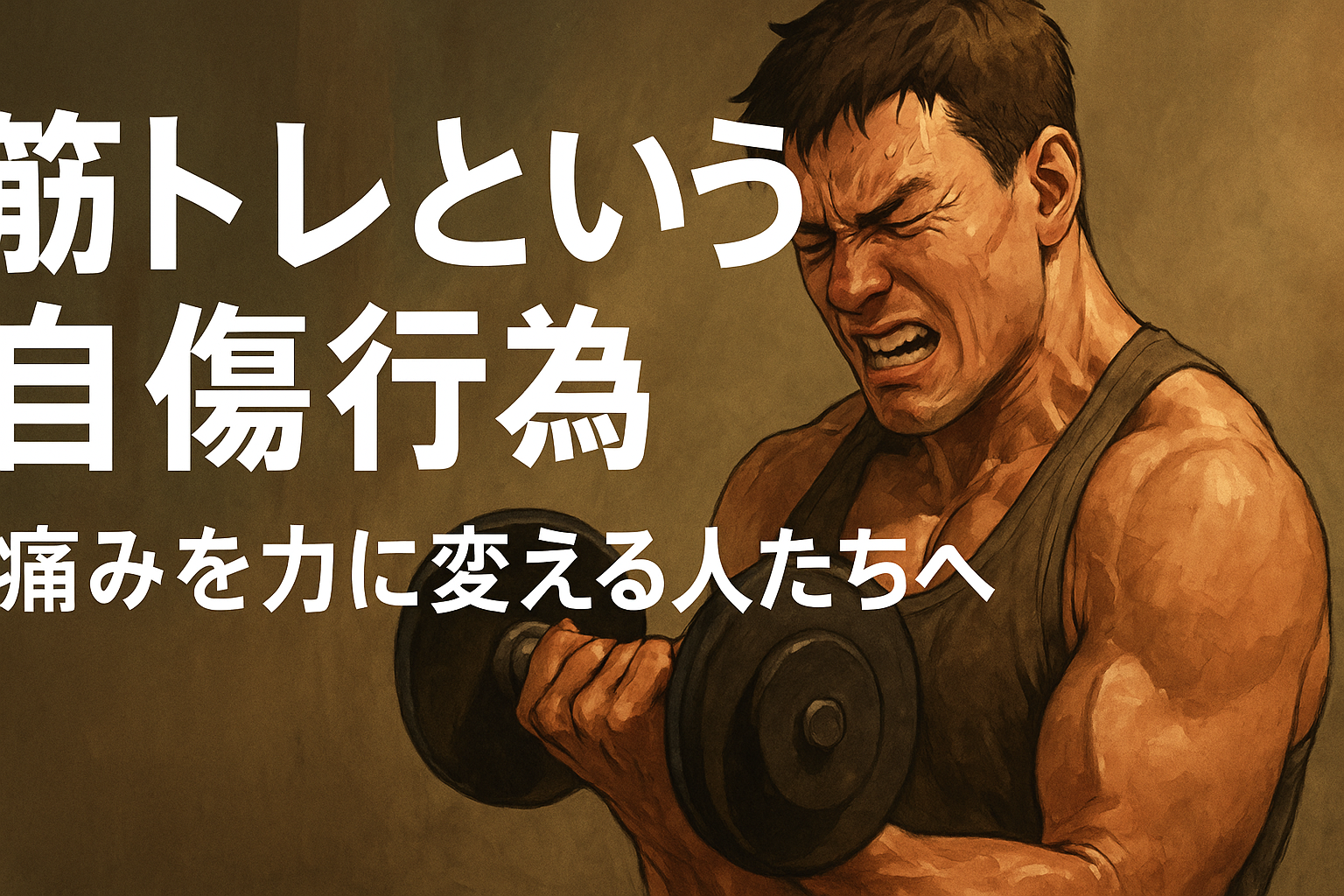
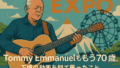
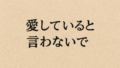
コメント