宮沢賢治って、やっぱり面白いんですよね。
大学時代に全集を読んだはずなのに、この「鳥箱先生とフウねずみ」はすっかり記憶から抜け落ちていました。
ところが先日、子どもが図書館から絵本を借りてきてくれて、久しぶりに再読。
「え?こんな話あったっけ?」と新鮮な気持ちで読み始めたのですが……やっぱり宮沢賢治、ちゃんと裏切ってきました。
あらすじ? ざっくり言えばこれだけ
「鳥かご先生とフウねずみの会話劇」。
はい、もうそれだけ。笑
内容を詳しく書くよりも、ぜひ自分で読んだ方がいいと思います。
特にラストがインパクト抜群です。
ネコの乱入と急展開
読み進めていくと、最後にいきなりネコが登場します。
そして言い放ったのが「先生もだめだし生徒もだめ」。
……え、なにそれ?
さっきまでゆるい掛け合いを眺めていたのに、急に人間批判みたいなことを言われて、物語はブツッと終了。
「急展開でわけわからん!」と正直思いました。
でも逆に、その唐突さが妙に面白いんです。
コントを見ていたら、いきなり社会派ニュースに切り替わったみたいで、肩透かしなのに余韻が残る。
これぞ宮沢賢治って感じ。
感じたテーマ
このラストに込められているのは、やっぱり人間批判だと思います。
「駄目なものが駄目なものを教育できるわけない」。
ストレートすぎるけど、どこか納得させられてしまう。
でも答えは示されない。問いだけを残して去っていく。
このモヤモヤ感がクセになるんですよね。
現代に当てはめると
現代にもそのまま当てはまると思います。
ただし完ぺきな人間なんていません。
だから結局は、不完全な者同士で刺激し合って、お互いを少しずつ高めていくしかない。
親も先生も上司も、みんなどこか駄目な部分を抱えている。
それでも関わり合って学び合っていくのが人間らしさなんだろうな、と感じました。
まとめ
久しぶりに読んだ「鳥箱先生とフウねずみ」は、やっぱり賢治らしくて、やっぱりわけわからなくて、でもやっぱり面白い作品でした。
学生の頃には記憶に残らなかったのに、今こうして子ども経由で再会し、大人の目線で“人間批判”を受け取る。
同じ作品でも読む時期によってまったく違う顔を見せる──文学って不思議ですね。
もし興味を持った方は、ぜひ原文を読んでみてください👇
〆



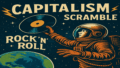
コメント